 キュウリの育て方
キュウリの育て方
きゅうりの育て方、土つくりから定植後の手入れや収穫まで
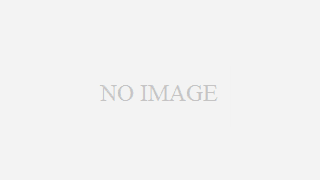 スイカの育て方
スイカの育て方 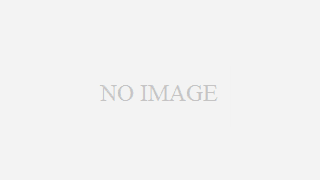 ズッキーニの育て方
ズッキーニの育て方 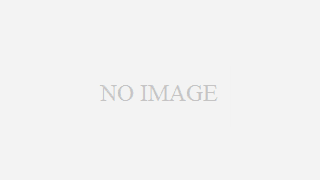 ズッキーニの育て方
ズッキーニの育て方 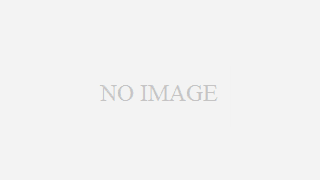 ズッキーニの育て方
ズッキーニの育て方 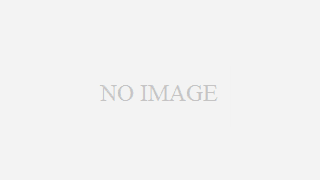 かぼちゃの育て方
かぼちゃの育て方 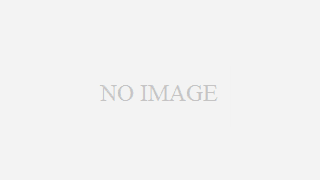 かぼちゃの育て方
かぼちゃの育て方 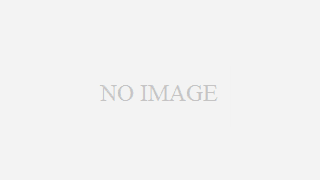 かぼちゃの育て方
かぼちゃの育て方 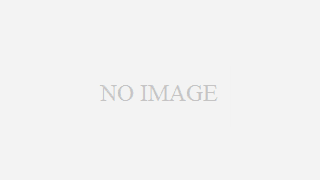 かぼちゃの育て方
かぼちゃの育て方 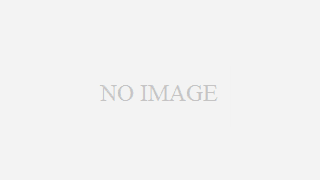 かぼちゃの育て方
かぼちゃの育て方 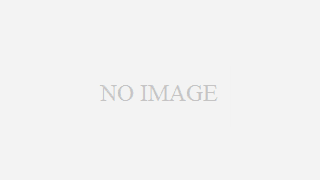 キュウリの育て方
キュウリの育て方